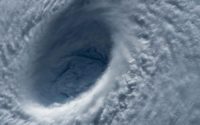賃貸マンションの原状回復問題はなぜ大岡裁き的のままなのか
賃貸マンションの原状回復に関する国土交通大臣のクレームについて、「住宅新報」がガイドラインに照らし合わせた確認を行なっています。
事の発端は、6/9の大臣会見で、旭化成不動産レジデンスが賃借人に対して発行した契約書が国交省の示している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に沿っていないので、実名を挙げて注意したというもの。
具体的には、畳の張り替えとハウスクリーニングの費用について「借主の故意や過失の有無にかかわらず借主が負担する」とする特約が入っている契約書を使い続けている点を指摘しています。
日本では、民法によって、お互いに交わした約束は実行されるように保護されています。ただし、その内容が法に違反するものであれば、その限りではありません。
賃貸マンションの賃貸借契約でも、原則としてはどんな条件を付しても法に触れない限りは有効であるということになります。
消費者の過剰な保護ではなくシステムの健全化を
ところが、契約時には気にしなかったけれど、解約時になんでもかんでも借り主が負担しなければならないような契約になっていたことに気づいて、トラブルになることが増えました。
これに対して、監督官庁の国交省が、消費者保護の猶予的な措置を目的に、原状回復ガイドラインを出していました。
6/9の大臣会見では、この流れに基づいて、国交省の方針に従わない契約のひな形を使っているのはイカンと怒ったわけです。
常識的に考えれば、借り主は家賃を払い、使用料とともにいわゆる減価償却を負担しているわけです。なのに、契約を終了するときになって契約時の状態まで戻せというのはぼったくりすぎではないかという声があがったというわけです。
住居の賃貸借については、土地と建物の所有権者の立場が強かったため、このような法的アンバランスが続いていました。近年ようやく東京ルールなどで是正の気運が高まり、国交省も腰を上げて、1998年、2004年、2011年と「借り主負担」の軽減を進めてきました。
負担の内容や割合に関しても、明示を強化していて、その結果、当該賃貸管理会社が内容的にガイドラインに沿ってないと指摘されるに至ったわけです。
ただ、今回の件に関して、担当部署である国交省賃貸住宅対策室では、旭化成不動産レジデンスの契約を「不適切と断言する要素はな」かったとの見解を示していると、住宅新報は報じています。
大臣が政治家特有のパフォーマンスをしただけとも取れますが、業界には効果のある牽制球になったかもしれませんね。
現状回復はケースバイケースで、なかなか一律に決められないことも多いでしょう。
それだけに、なんとなく弱きを助けるふりをして流れを作るのではなく、使用前使用後の記録の整備など、論理的なシステムの整備で、誰もが納得できる方向へ導いてもらいたいものだと願っています。